カリキュラム・時間割
新しい法学科へ
時代のニーズに応えるべく、法学科はカリキュラムを大幅に改正しました。
手厚い少人数教育の充実など、法学科には新たな魅力が満載です。
基礎教育の重視
法科大学院の設置に伴い、学部段階では法学・政治学の基礎固めを重視します。法学・政治学を学びたいという学生の若々しい気持ちに、瑞々しい感性を備えた教員が存分に応える、そんな仕組みを整備しました。
コミュニケーションリテラシーに関する科目
普遍教育科目では、大学生の基礎的な素養としてコミュニケーション能力を重視し、これに関する科目として、「英語科目」「初修外国語科目」「情報リテラシー科目」を必修科目として用意しています。「初修外国語科目」は、英語以外のはじめて触れる外国語の運用能力を育成し、多様な価値観・異文化を理解し、尊重する姿勢を身につけることが目標です。「情報リテラシー科目」は、たんにコンピュータやネットワークの使用方法の習得ではなく、これらが社会において果たす役割、情報に係わる論理的役割を理解し、あわせて、その使用にともなう倫理的問題を修得することを目標にします。
教養コア科目
教養コア科目は、「A 論理と哲学」「B こころと発達」「C 芸術と文化」「D 社会と歴史」「E くらしと環境」「F いのちと科学」の6つの科目群からなります。こられは、大学で何を学んでいくのかを、全学部の先生方がご自身の学問を通して伝えていくものです。それぞれの科目群から1科目を選択し、履修することが必要です。
教養展開科目
教養展開科目は、教養コア科目の履修を通して喚起された学問への興味・関心をさらに拡大、進化させ、豊な教養へと結びつけることを目的として開講されます。隣接する領域についての知見を深め、異なる学問の世界への視野を広げるとともに、学んだ知識を経験として自分のものにし、自ら課題を見いだし、解決する能力を育てていくことをねらいとしています。
専門教育科目
必修科目が少なく、数多い専門科目から幅広く選択して自由に勉強できることが、法学科の特徴となっています。専門教育科目は、基礎をつくる「専門基礎科目」と、本格的な法学・政治学の勉強をする「専門科目」に分類されています。
専門基礎科目
専門基礎科目は、「必修科目」「選択必修科目」「選択科目」の3つからなっています。まず1年次指定の「基礎ゼミ」が必修であり、そこで専門科目の勉強の仕方(本の読み方、レジュメの作成の仕方、文章の書き方など)をゼミ形式によって学びます。
選択必修科目は、「日本近代法史」か「裁判法」のいずれかを、必ず履修することになっています。前者は、歴史的な観点から、わが国の現在の法体系がどのように作られてきたのかを説明し、高校までの学習内容との連続を図ります。また後者は、裁判・法的紛争に関わる「人」にはどのような人がいるのか、という観点から、法律問題を身近に感じられるようにすることをねらっています。
選択科目は、「民刑事法入門」と「政治学入門」です。前者は、民法および刑法の導入と同時に、法学全般の導入となるように位置づけています。また後者は、政治学全般に関する導入科目として、専門科目を履修するための準備的な内容を講義します。
専門科目
専門科目は、「民法総論」「憲法A」「刑法A」の3科目が必修となっています。必修以外は、基本的に専門科目一覧の中から自由に選択して勉強することができます。必修科目の数が多すぎると、その勉強が忙しくて、もともと自分の取りたかった科目に手が回らない、ということも起こりがちです。悔いのない勉強をするために、選択の幅の広さを活かしてください。大きく法律学と政治学の科目からなっていますが、両者は極めて密接なつながりがあるものですので、自分の問題関心と進路などを考慮しながら、それぞれの科目内容を適切に結びつけ、幅広い知識と思考能力を身につけてもらいたいと思います。
法経学部他学科科目の履修
法学・政治学が人間社会についての学問である以上、法学・政治学以外の分野についても、知っておく必要があります。千葉大学法経学部法学科は、経済学科、総合政策学科と一緒になってひとつの学部を構成しているという特色を生かして、他の2学科と緊密に連携して、教育体制を組んでいます。経済学科や総合政策学科の科目をいくつか履修しないと卒業できないので少し大変ですが、あとでかならず納得できるシステムです。
基礎ゼミの必修化
 新入生は全員、1クラス30名の基礎ゼミに所属します。このクラスでは、法学・政治学を学ぶための足場を固めるとともに、クラスメイトや担当教員との豊かな人間関係の構築を支援します。また基礎ゼミ担当教員は、クラス担任として卒業まで皆さんのキャンパスライフをサポートしていきます。
新入生は全員、1クラス30名の基礎ゼミに所属します。このクラスでは、法学・政治学を学ぶための足場を固めるとともに、クラスメイトや担当教員との豊かな人間関係の構築を支援します。また基礎ゼミ担当教員は、クラス担任として卒業まで皆さんのキャンパスライフをサポートしていきます。

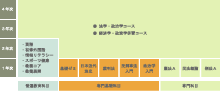
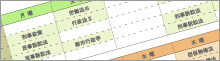
 多様化する皆さんのニーズに応えるべく、法学科では、伝統的な法学・政治学のトレーニングを中心とする「法学・政治学コース」に加え、更に視野を拡げる「経済学・政策学併習コース」を設置し、入学後にそのいずれかを選択する制度を用意しています。
多様化する皆さんのニーズに応えるべく、法学科では、伝統的な法学・政治学のトレーニングを中心とする「法学・政治学コース」に加え、更に視野を拡げる「経済学・政策学併習コース」を設置し、入学後にそのいずれかを選択する制度を用意しています。